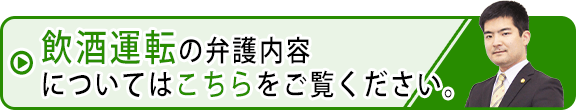「交通犯罪」に関するお役立ち情報
飲酒運転で適用される刑罰
1 飲酒運転とは
飲酒運転は、アルコールを摂取した後に、アルコールによる影響がある状態において自動車や単車(オートバイなど)などの車両を運転することです(自転車もこれに含まれます)。
飲酒運転は、昔は重くは罰せられなかったのですが、悪質な飲酒運転による交通事故が相次いで社会問題となったことなどから、徐々に厳罰化されています。
法的に、飲酒運転には刑罰の重さという観点から「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
⑴ 酒気帯び運転
「酒気帯び運転」とは、飲酒運転の中でもアルコールによる影響が軽い場合です。
飲酒していても、正常に運転をすることが期待できる状態ならば「酒気帯び運転」となります。
酒気帯び運転に該当するかどうかについては、呼気内のアルコール量を測ることにより決定します。
基準として、呼気1リットルにおいて0.15mg以上のアルコール量が検出されると酒気帯び運転です。
血液1ミリリットルにおいて0.3mg以上のアルコール量が含有されている状態でも酒気帯び運転となります。
このように、酒気帯び運転の基準は非常に明確であり、外見上酒による影響が分かりやすい人でも分かりにくい人でも、呼気量検査によって機械的に違反を検出することができます。
⑵ 酒酔い運転
これに対して、「酒酔い運転」の基準は客観的には明らかではなく、「アルコールの影響により、正常に運転できないおそれがある状態」というものです。
酩酊状態でふらふらになっていたり、「ろれつ」が回らなくなっていたりする状態です。
そこで、酒酔い運転になるかどうかについては、人によって基準が異なります。
酒に強く、酔いが回りにくい人は酒酔い運転になりにくいですし、反対に、酩酊状態になりやすい人であれば、少量の飲酒でも酒酔い運転になります。
2 飲酒運転で適用される刑罰
次に、上記のような飲酒運転で適用される可能性のある刑罰を確認しましょう。
⑴ 道路交通法違反
道路交通法は、飲酒運転をしたときに罰則を適用しています。
飲酒運転については年々厳罰化されていますが、最新では2007年に変更されて、以下の通りになっています。
酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
最近では、1回目の道路交通法違反で罰金刑が適用されても、2回目になると公判請求され、拘禁刑を選択されるケースが増えてきています。
また、警察官などによる呼気検査を拒絶した場合にも、罰則が適用されます。
なお、酒に酔った人に車両を提供した人や、運転しようとしている人に酒類を提供した人にも、刑事罰が適用される可能性があります。
⑵ 自動車運転処罰法
飲酒した状態で交通事故(人身事故)を起こすと、「自動車運転処罰法」という法律による刑罰が適用されて、罪が非常に重くなります。
自動車運転処罰法にもとづく代表的な犯罪と刑罰は、以下の通りです。
・過失運転致死傷罪
・危険運転致死傷罪
・アルコール等影響発覚免脱罪
①過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
過失運転致死傷罪は、通常期待される注意を払わなかったために交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合に成立する犯罪です。
例えば、飲酒運転で前方不注視、脇見運転、ハンドル操作不適切などによって事故を引き起こした場合、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
※ただし、アルコールによる影響が大きく、正常な運転をすることが難しい場合には、そのような状態で運転すること自体が非常に危険なので、通常の過失とは言えず、次に紹介する危険運転致死傷罪が成立します。
過失運転致死傷罪による刑罰の内容は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑です。
傷害の程度が軽いときは、情状によって刑を免除されることもあります。
ただし、飲酒運転の場合、道路交通法違反と過失運転致死傷罪が両方成立するので「併合罪加重」されてしまいます。
この場合、長い方の刑の刑期が1.5倍となるので、拘禁刑10年6月以下となります。
また、ひき逃げをした場合には、併合罪加重によって拘禁刑15年以下となります。
②危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)
危険運転致死傷罪とは、通常の過失の範囲を超えて、故意とも同視しうるような危険な方法で運転をして人と死傷させた場合に成立する犯罪です。
アルコールにより、正常な運転ができない状態(酒酔い運転)で交通事故を起こすと、多くのケースで危険運転致死傷罪の責任を問われます。
危険運転致死傷罪の罰則は、被害者が傷害を負ったケースで15年以下の拘禁刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期拘禁刑となります。
罰金刑はなく、初犯でも必ず拘禁刑を適用されます。
また、飲酒運転の場合、道路交通法違反にもなるため、やはり併合罪加重が行われます。
危険運転致傷罪と道路交通法違反が成立する場合には、拘禁刑15年の1.5倍となるので、最高22年6月以下の拘禁刑です。
被害者が死亡してしまった場合には、最高30年(有期拘禁刑の限度)の拘禁刑となってしまいます。
③アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転処罰法3条)
アルコールを摂取した状態で交通事故を起こすと、上記のように非常に重い刑罰を適用されてしまうので、アルコールによる影響が発覚しないように逃げてしまう人がいます。
この場合、本来は通常の過失運転致死傷罪が成立するはずだったケースでも、「アルコール等影響発覚免脱罪」というより重い犯罪が成立してしまいます。
こうなると、被害者がケガをした場合に12年以下の拘禁刑が適用されるので、刑罰が大きく加重されます。
【ひき逃げの場合の刑罰】
飲酒運転をした状態で交通事故を起こすと、ひき逃げをしてしまうことが少なくありません。
アルコールが抜けるまで時間稼ぎをしようと思うこともあるでしょうし、怖くなって思わず逃げてしまうこともあります。
酔っていたので事故を起こしても気づかなかった、ということもあるかもしれません。
しかし、人身事故を引き起こした人は、すぐに被害者を救護して危険を防止し、警察に通報する義務を負っています。
この義務を怠ると、報告義務違反として(道路交通法72条・117条第2講)道路交通法によって10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑が適用されます。
この報告義務違反の罪も、過失運転致死傷罪などとは併合罪の関係になりますので、ひき逃げをすると、刑罰がさらに加重されることになります。
お役立ち情報トップへ 痴漢で不起訴・前科の回避を目指す方法とは