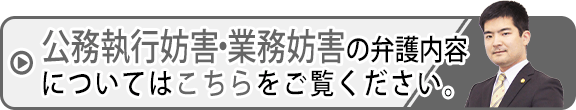「その他」のお役立ち情報
公務執行妨害罪の成立要件
1 公務執行妨害罪とは
公務員に対し暴行・脅迫をした場合、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいます。
公務執行妨害罪の構成要件は刑法95条1項に定められています。
【刑法95条1項】
“公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。”
公務員とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)を指します。
警察官や消防士、市役所の職員などは公務員に該当します。
公務執行妨害罪の法定刑は①3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっています。
すなわち、公務執行妨害罪で逮捕された場合には拘禁刑が科され刑務所に収監される可能性があります。
⑴ 公務員の「職務」の範囲
区役所内で騒いでいる被告人を注意した区役所職員に対し、右肩を手で押し転倒させた行為について公務執行妨害罪が成立する(東京高判平成27年7月7日LEX/DB25545241)
公務執行妨害罪は、「職務」を「執行するにあたり」「暴行・脅迫」を加えた場合に成立します。
公務執行妨害罪は、公務の円滑な執行を保護するもので、保護の必要性は公務の性格にかかわらないことから、「職務」には広く公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれます。
このため、警察官の逮捕手続きなどのように、公権力を行使して強制力をもって国民の権利を制限する活動が含まれるのはもちろんですが、そうでなくとも、警察官による単なるパトロールや、例えば市役所の事務職員が行うような民間企業従業員とかわらない書類作成作業などを妨害した場合にも、公務執行妨害罪は成立します。
なお、条文には書かれていませんが、「職務」は適法な職務であることが必要です。
違法な職務は保護に値しないためです。
少なくとも、法律上の手続き・方式の重要部分が実行されていれば適法な職務と判断されるでしょう。
また、暴行・脅迫は「職務を執行するにあたり」行われる必要があります。
円滑な公務執行の保護が目的ですから、個別具体的に特定された職務執行行為の開始から終了までの間に暴行・脅迫が加えられた場合を原則とします。
これを示したのが、次の判例です。
国鉄の助役が職員の点呼終了後に次の職務である事務引継ぎに赴くに際し、その助役に暴行を加えても、公務執行妨害罪は成立しない(最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1812頁)
したがって、非番や休憩中の警察官に暴行を加えても公務執行妨害罪は成立しません。
しかし、その警察官個人の身体の安全を保護する暴行罪や傷害罪には問われます。
公務の執行中か否かは、実質的な観点から判断するべきとされています。
例えば次の判例は、県議会の委員会において休憩が宣言された後であっても、公務執行妨害罪との関係では、その委員長の職務は継続していたと評価しています。
県議会委員長が休憩を宣言し退席しようとした際に暴行を加える行為に公務執行妨害罪が成立する(最判平成元年3月10日刑集43巻3号188頁)
⑵ 「暴行又は脅迫」の程度
公務執行妨害罪は公務の円滑な執行を保護するものですから、暴行・脅迫は「公務を妨害するに足りる程度のもの」であればよく、しかも現実に妨害されたことは不要です。
このため、非常に軽度の有形力の行使であっても、公務執行妨害罪に問われるのが実際です。
例えば、以下の裁判例があります。
“第一審では、検察官は被告人が警察官を突き飛ばしたと主張しましたが、裁判所は、そのような事実は証拠上認定できないとしました。ところが一方で裁判所は、警察官の両肩を両手で数回押さえつけただけの行為等をとらえて、これを公務執行妨害罪の暴行であるとして、結局、公務執行妨害罪の成立を認めました。被告人は控訴しましたが、高裁は原審を支持して控訴を棄却しました(東京高判令和元年11月8日・最高裁判所刑事判例集74巻1号267頁)。”
また、暴行罪の暴行は、必ずしも被害者の身体に接触する必要はありませんが、少なくとも人の身体に向け行われる必要があります。
暴行罪は身体の安全を保護するものだからです。
これに対し、公務執行妨害罪は、公務の円滑な執行を保護するものですから、同罪の暴行は、被害者の身体に接触する必要がないことはもちろん、公務員の面前で行われる限りは、その身体に向け行われる必要もありません。
次の判例が参考になります。
“司法巡査が逮捕現場で差押えた覚醒剤を足で踏みつけて損壊する行為に公務執行妨害罪が成立する(最判昭和34年8月27日刑集13巻10号2769頁)”
したがって、警察官の面前で、同人が乗ってきたパトカーや自転車を殴る蹴るなどした場合にも公務執行妨害罪は成立します。
2 公務執行妨害罪で逮捕された後の流れ
公務執行妨害罪を犯した場合、ほとんどはその場で現行犯逮捕されるでしょう。
逮捕された場合、身柄は警察署に移され、そこで取調べを受けます。
そして、逮捕から48時間以内に身柄は検察官に移され、その後検察官からも取調べを受けます。
そして、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官は被疑者の勾留を請求するか否か決定します。
勾留請求が認められると被疑者は勾留請求の日から最大20日間身体拘束されます。
逮捕は最大で3日間(72時間)、勾留は最大で20日間なので、起訴前の身体拘束は最長で23日間続きます。
検察官は、勾留期間が満了するまでに被疑者を起訴するか否かを決定します。起訴されなかった場合身柄は釈放されます。
起訴された場合にはその後裁判となります。
起訴後も保釈が認められない限り、身体拘束が継続されます。
3 逮捕された場合に弁護士に相談すべき理由
⑴ 弁護士なら面会・アドバイスができる
先述のように、逮捕された場合には最大3日間身体拘束されます。
その間、家族の方ですら本人と会うことはできません。
しかし、弁護士であれば接見が可能なので、伝えたいことがあったり、差し入れをしたかったりする場合、これを弁護士に依頼することができます。
また、逮捕されている本人としても、取調べにおいてどのように対応すればいいか弁護士からアドバイスを受けることができます。
⑵ 公務執行妨害罪と示談
公務執行妨害罪は公務員個人を守るための法律ではなく、公務の円滑な執行という国家作用を守る法律です。
国や地方公共団体が、このような公的な利益を自由に処分できるわけではありませんから、公務執行妨害罪において、国や地方公共団体との示談ということは通常は考えられません。
そこで、被疑者としては、反省文を書いて弁護士から検察官・裁判官に提出してもらう、弁護士会などへ贖罪寄付(一定の金銭を寄付すること)をするなどして、示談以外の方法で、真摯な反省を示すことになります。
ただ、国や自治体に金銭的な損害も生じた場合は、当然、加害者には民事賠償の責任が生じます。
また、例えば暴行を受けた公務員が怪我をした場合には公務員個人に対する傷害罪も別途成立し、加害者は、その個人への賠償義務も負担します。
これらの場合には、国や自治体、公務員個人への民事賠償をするために、それぞれと弁護士を通じて示談交渉を行います。
これらの示談が成立すれば、起訴不起訴の判断や量刑にあたって、犯人に有利な情状として考慮されることはもちろんです。
⑶ 弁護士から検察、裁判所への働きかけ
さらに弁護士としては、検察官や裁判官に被疑者の身体拘束を継続しないよう、また検察官に起訴をしないよう働きかけます。
身体拘束されている方は、自らに有利な証拠を収集することが困難です。
また、法律(刑法、刑事訴訟法など)に精通していなければ、公務執行妨害の適切な弁護活動はできません。
そのため、公務執行妨害罪で逮捕されたら、即刻刑事事件に詳しい弁護士に相談すべきです。
もし公務執行妨害罪で逮捕されたら、まずは弁護士にご相談ください。
在宅事件となった場合の流れ 川越で刑事事件について弁護士をお探しの方へ